
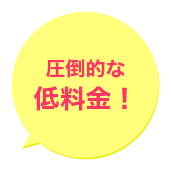
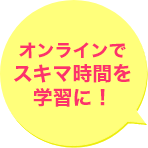
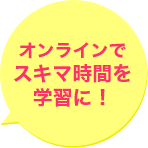
「サービス終了のお知らせ」
平素は「ManaBun大学受験対策コース」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび2024年3月31日をもちまして、 サービスの提供を終了させていただくことになりました。 これまで多くの受講生様にご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
※サービス終了にともないまして、2024年2月20日以降の無料トライアルも終了させていただきます。
※「ManaBun資格講座」は引き続きサービスを行っております。



\ 講義は東大生監修で分かりやすい! /

講座毎に別料金は発生しません。月額550円(税込)ですべての講座を受講いただけます。
\ 大充実の豊富なラインナップ /

インプットとアウトプットを繰り返し、短時間でも効率の良い学習を実現できます。

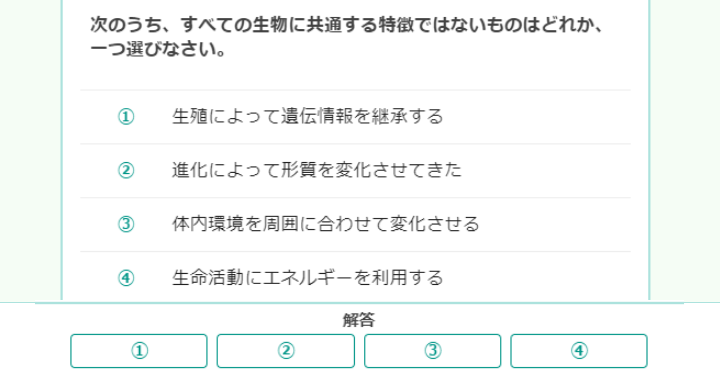

いつでもどこでも スキマ時間で学習!

